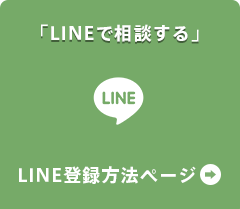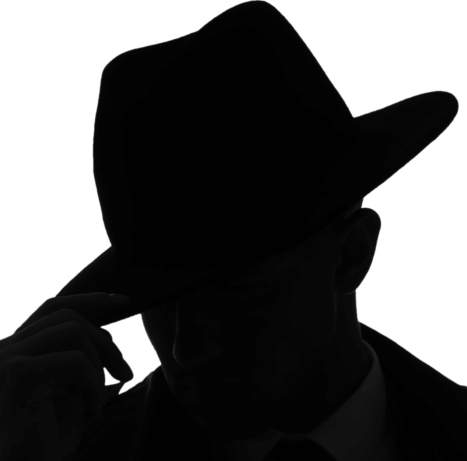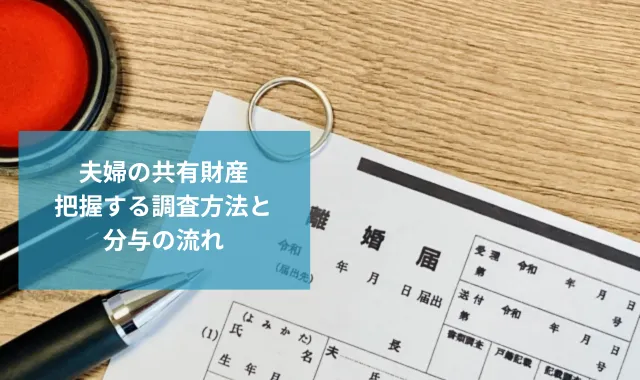
夫婦が離婚する際には、共有財産分与が行われます。
ただし、適切に分与を行うには、どのような財産が共有財産となるのかを理解し、相手に隠し財産がないか調べる必要があります。
本記事では、共有財産を把握する方法や分与の流れ、財産の調査方法について詳しく解説します。
目次
夫婦の共有財産とは?

夫婦が離婚となる場合に、重要になるのが共有財産です。
しかし、共有財産がどのような財産なのか、知らない方もいらっしゃるでしょう。
ここでは、夫婦の共有財産の概要について解説します。
共有財産の法的な定義と民法における位置づけ
夫婦の共有財産とは、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産であり、民法に明確な規定があります。
民法第762条は「夫婦の一方が婚姻中に得た財産は、特段の合意がない限り夫婦の共有と推定する」と定めています。
つまり、夫婦のどちらか一方の名義になっていても、婚姻生活を支えるために形成された財産は共有とみなされるのです。
たとえば、共働き家庭で夫婦それぞれが収入を得ている場合、その収入や貯蓄は原則として共有財産に含まれます。
また、専業主婦(主夫)の家庭であっても、もう一方の配偶者が働いて得た収入や、それをもとに購入した財産は、夫婦双方の協力によって得られたと解釈されます。
離婚や相続の場面では、どの財産が共有財産に当たるのかを正しく理解することが重要です。
夫婦別財産制と共有財産制の違い
日本の法律は「夫婦別産制」を基本としています。
これは、婚姻前から各自が持っていた財産や、婚姻中に相続や贈与によって取得した財産は、それぞれの個人に属するという制度です。
一方で、婚姻中に収入や労働によって築かれた財産は「共有財産」として取り扱われます。
たとえば、結婚前に夫が持っていた貯金は夫の特有財産であり、離婚時に分与対象にはなりません。
しかし、結婚後にその貯金から生活費を支出し、残高が増減した場合には、その動きが共有財産とどのように関連しているのかを精査する必要があります。
また、海外では夫婦共有財産制を採用している国も多く、婚姻後の財産は全て自動的に共有される仕組みがあります。
日本の場合は夫婦別産制を基本にしながらも、生活実態に応じて「共有財産」と認められる範囲を広げているため、実務では複雑な判断が伴うのが実状です。
夫婦の婚姻生活と財産形成の関係性
夫婦の共有財産が成立する背景には、婚姻生活における協力関係があります。
日々の生活を維持するためには、収入を得る人と家庭を支える人、それぞれの役割が必要です。
専業主婦(主夫)が家事や育児を担い、もう一方の配偶者が収入を得るという形であっても、財産形成は夫婦双方の貢献によって成り立っていると評価されます。
この考え方は、家庭内労働の価値を法的に認めるものでもあります。
そのため、夫婦の一方が「自分が稼いだお金だから自分のもの」と主張したとしても、法律上はそう単純には扱われません。
実際に、裁判例でも家事労働を果たした配偶者の寄与が共有財産の形成に貢献したと認められることが多くあります。
つまり、夫婦で築いた財産は二人の努力の成果であり、どちらか一方だけの所有物とは考えないのが基本です。
「名義」と「所有権」の違いが共有財産判断に与える影響
共有財産を考える際に誤解されやすいのが、「名義」と「所有権」の違いです。
たとえば不動産の登記簿や預金通帳に夫の名前だけが記載されている場合、多くの人はその財産が夫のものだと考えがちです。
しかし、法律的には名義と所有権は必ずしも一致するわけではありません。
婚姻中の収入をもとに購入した不動産や預金は、名義がどちらであっても共有財産であると推定されるためです。
逆に、名義が夫婦連名でも、実際には一方の特有財産で購入した場合には共有財産とならないケースもあります。
このように、名義はあくまで便宜的な記録にすぎず、実際の所有権が誰にあるのかは財産の取得経緯によって判断されます。
そのため、離婚時や相続時に財産を分ける際には、名義に惑わされず、その財産がどのような資金から形成されたのかを丁寧に確認することが重要です。
夫婦の共有財産に含まれる具体的な財産の種類

夫婦の共有財産の概要を理解できたところで、ここからは共有財産とみなされる具体的な財産の種類を紹介します。
これらの財産の種類を知ることで、離婚時に適切な財産分与ができるようになります。
不動産(家・土地)が共有財産に該当するケース
夫婦にとって大きな資産となるのが、住宅や土地といった不動産です。
不動産が共有財産となるかどうかは、購入した時期や資金の出どころによって判断されます。
婚姻中に夫婦の収入をもとに住宅ローンを組んで購入した場合、その不動産は原則として共有財産とみなされます。
名義が夫だけ、あるいは妻だけになっていても、実際の資金が婚姻生活から生じたものであれば夫婦の共有財産に該当するのです。
一方で、結婚前から所有していた土地や、親から相続した実家をもとに建てた家などは「特有財産」として扱われ、分与の対象外となる場合があります。
ただし、特有財産を利用して新たにリフォームしたり、ローン返済を婚姻中の収入で行った場合には、共有財産との境界が複雑になることも少なくありません。
不動産は高額であるがゆえに、離婚や相続における争点になりやすい財産の代表例といえます。
預金や貯金口座はどのように扱われるか
預金や貯金は、日常生活の中でも身近な資産です。
婚姻中に給与や事業収入から積み立てられた預金は、名義が夫であっても妻であっても共有財産とみなされます。
通帳や口座が一方の名前で管理されている場合でも、その中身が夫婦の努力によって築かれたものであれば、分与の対象になるのが原則です。
ただし、結婚前から保有していた貯金や、婚姻中に受けた相続金は特有財産として区別されるため、同じ口座に入金していると判断が難しくなります。
たとえば、相続金を生活費用の口座に移した場合、その後の入出金が混ざり合ってしまい、どこまでが特有財産なのか明確に線引きできなくなることもあります。
こうした問題を防ぐためには、婚姻前からの資産や相続金を専用の口座で管理することが望ましいといえるでしょう。
給与や賞与など労働による収入の扱い方
婚姻中に得た給与や賞与は、夫婦双方の協力によって得られたとみなされ、共有財産に含まれるのが原則です。
仮に夫が会社員として働き、妻が専業主婦であっても、妻の家事労働や育児の貢献がなければ夫の収入を安定して得られなかったと考えられるためです。
また、歩合制やフリーランスの収入の場合も、婚姻中に得た報酬であれば共有財産とされるのが基本です。
一方で、婚姻前に勤務していた会社から結婚後に支払われた退職金や、婚姻期間外に働いた分の報酬は、共有財産には含まれない場合があります。
労働による収入は、名義人が誰かにかかわらず、婚姻生活を支えるために得られた成果とみなされます。
車や家具など動産の共有財産としての判断基準
車や家具などの動産も、婚姻中に取得した場合は共有財産に該当します。
たとえば夫名義で購入した自動車であっても、その資金が夫婦の収入から出ていれば、妻もその所有権を主張可能です。
また、テレビや冷蔵庫といった家電や家具も、婚姻中の生活を支えるために購入したものであれば共有財産として扱われます。
一方で、個人的な趣味のために高額なカメラやコレクションを購入した場合、それが生活に必要かどうかで判断が分かれます。
また、婚姻前に購入した車や家具は特有財産として扱われるため、分与の対象にはなりません。
こうした動産は不動産や預金に比べると価値が低いように思われがちですが、離婚時には数十万円単位で分与の対象になるケースもあります。
特に車は資産価値が高いため、共有財産に当たるか正しく判断することが大切です。
共有財産の管理と運用のルール

離婚時には、残った財産が共有財産かどうかが重要になります。
そのため、共有財産と特有財産は区別して管理・運用されなければなりません。
ここでは、夫婦での共有財産の管理の仕方や運用方法について解説します。
夫婦での合意が必要となる財産の処分行為
共有財産を処分する際には、夫婦双方の合意が必要となる場面があります。
特に不動産の売却や抵当権の設定など、金額的に大きな影響を及ぼす行為は一方の判断だけでは無効となる可能性が高いのです。
民法第761条は、夫婦が同居し、協力し合う義務を定めており、その延長として重要な財産行為には共同の意思決定が求められると解釈されます。
これは夫婦の一方が、不利益を被ることを防ぐために設けられた仕組みです。
仮に夫が妻に無断で家を売却した場合、後にその売却が無効とされるケースもあり得ます。
共有財産を守るには、夫婦間で事前に十分な話し合いを行い、同意を得た上で処分することが欠かせません。
こうした合意形成のルールを理解すれば、財産をめぐる無用なトラブルを避けられるでしょう。
日常的な買い物と高額取引の法的取り扱いの違い
夫婦の生活では、日常的な支出と高額な取引が発生します。
食料品や日用品といった日常の買い物は、生活維持に不可欠であるため、夫婦の一方が自由に行っても法律上問題とはされません。
一方で、高額な財産を購入したり売却したりする場合には、夫婦の合意が必要です。
たとえば自動車や高額な宝飾品、不動産などを購入する際には、一方の判断だけでは後に無効となる可能性があります。
生活費に関わる範囲は柔軟に扱い、それ以外の大きな支出は夫婦の共同決定が前提になるという仕組みです。
この線引きを理解することで、家庭内での金銭トラブルを未然に防ぎやすくなります。
預金や投資商品の管理を夫婦でどう分担するか
共有財産の中でも預金や投資商品は、適切な管理が求められる資産です。
夫婦の一方が全てを管理していると、もう一方が状況を把握できず、不信感を抱く原因になります。
望ましいのは、口座や投資状況を夫婦で共有し、透明性を確保することです。
たとえば、夫が給与口座を管理し、妻が生活費用の口座を管理するなど、役割を分担するのがおすすめです。
また、投資信託や株式などリスクのある商品については、夫婦で定期的に確認し合うことでリスク共有が可能になります。
財産の可視化は、離婚や相続時のトラブル防止にもつながる重要なステップといえるでしょう。
共有財産を一方が勝手に処分した場合の問題点
夫婦の同意なく一方が共有財産を処分すると、大きな問題に発展する恐れがあります。
特に不動産や高額な動産を無断で売却した場合、その行為は無効や取り消しとなることもあるため、注意しなければなりません。
また、勝手に預金を引き出したり、投資資金を使い込んだりすると、後に裁判で責任を問われる可能性もあります。
法律は夫婦双方の利益を守るために、重要な財産行為には合意を必要とする仕組みを整えています。
にもかかわらず無断で処分を行えば、信頼関係が壊れるだけでなく、財産分与時に不利な判断が下されることも少なくありません。
財産を勝手に扱うことなく、日頃から透明性のある管理を行うのが重要です。
離婚時における共有財産分与の仕組み

離婚に至る場合、夫婦の共有財産はそれぞれに分与されることになります。
ここでは、共有財産分与の仕組みについて詳しく解説します。
財産分与の基本原則と平等分与の考え方
離婚時の財産分与では、夫婦が婚姻中に協力して築いた財産を公平に分け合うことが基本です。
日本の裁判所は「原則として2分の1ずつ分ける」という平等分与の考え方を採用しています。
たとえば、夫婦が共同で購入した不動産や婚姻中に積み立てた預金は、名義が一方のみであっても、実際には夫婦の共有財産として半分ずつ分けられるのです。
このルールでは、家事労働や育児も財産形成に寄与したと評価されるため、専業主婦(主夫)であっても分与の権利を有します。
「稼いでいないから権利がない」という考えは誤解であり、婚姻生活の中で果たした役割全体が評価対象となるのです。
寄与度の有無が分与割合に影響するか
財産分与において原則は二分の一の平等分与ですが、場合によっては寄与度が考慮されることがあります。
たとえば、一方が多大な収入を得て家計を大きく支えた場合や、もう一方が浪費を繰り返して財産形成を阻害した場合などは、分与割合に修正が加わる可能性があります。
ただし、裁判所は家事や育児の労働を経済活動と同等に評価するため、専業主婦・主夫の立場が不当に低く扱われることは基本的にありません。
寄与度が考慮されるのは例外的なケースに限られ、著しい不公平が生じると判断される場合です。
実際には「よほど極端な事情がない限り、原則通り二分の一ずつ」とされるのが実務の運用です。
離婚協議・調停・裁判での共有財産分与の流れ
離婚に伴う財産分与は、まず当事者同士の話し合い(協議)から始まります。
協議離婚が成立すれば、公正証書などで合意内容を残しておくことで将来的なトラブルを防げます。
しかし協議で合意に至らない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てます。
調停では調停委員を介して話し合いが行われ、双方が納得できる妥協点を探ります。
それでも合意できなければ裁判へ移行し、最終的に裁判所が判断を下すのが一般的です。
裁判では財産の範囲や価値、寄与度などを踏まえた分与割合が決定され、法的拘束力を持ちます。
この流れで重要なのは、早い段階から財産を正確に把握し、証拠を確保することです。
協議で解決できれば費用や時間を大幅に節約できますが、対立が激しい場合は調停や裁判を視野に入れた準備が必要となります。
家庭裁判所での財産分与判断の基準
家庭裁判所が財産分与を判断する際には、いくつかの基準が用いられます。
第一に「共有財産か特有財産か」の区別であり、婚姻期間中の収入や貯蓄は共有財産とされやすい一方、相続や贈与財産は特有財産に分類されます。
第二に「寄与度の有無」で、前述のとおり原則は平等ですが、浪費や不正な使途が認められる場合には修正が行われる可能性があります。
また、退職金や年金といった将来受給予定の財産についても、婚姻期間中に形成された部分が対象となることがあります。
裁判所は証拠に基づき客観的に判断するため、預金通帳の記録や不動産登記簿などの証拠資料が重要です。
裁判で争う場合、事前にどの財産が対象になるかを整理しておくことが、適切な結果を得るうえで欠かせません。
共有財産の調査・把握の方法

離婚時の共有財産分与のためには、対象となる財産の把握や整理が重要になることが分かりました。
ここからは、共有財産を調べ、把握するための方法について解説します。
銀行口座や証券口座の残高確認方法
共有財産を把握するうえでまず確認すべきは、銀行口座や証券口座です。
婚姻期間中に得た収入から積み立てられた預金や投資資産は原則として共有財産に該当します。
具体的には、通帳や取引明細を取得し、残高や入出金履歴を精査することが必要です。
もし配偶者が通帳を隠している場合でも、金融機関に対して取引履歴の開示請求を行うことが可能です。
また、証券口座においては保有株式や投資信託の評価額を確認し、時価ベースで資産額を算定します。
調査の際には、口座が複数存在する場合を想定し、漏れなく把握することが重要です。
不動産登記簿や権利証を用いた確認
不動産は共有財産のなかでも高額かつ重要な資産です。
婚姻期間中に購入した自宅や投資用不動産は、登記名義が一方の配偶者になっていても共有財産とみなされる場合があります。
その確認に用いられるのが不動産登記簿です。
登記簿には所有者や抵当権の有無が記載されており、法務局で取得可能です。
また、権利証や固定資産税の納付書なども参考資料となります。
注意すべきは、名義だけで判断せず、購入資金の出所を確認することです。
たとえば、一方の相続財産を充てて購入した場合は特有財産扱いとなる可能性があります。
不動産は価値が大きいため、確実な情報収集を行い、財産分与で不利益を被らないよう準備することが重要です。
退職金や年金など将来受け取る財産の確認
退職金や年金は将来受け取る性質の財産ですが、婚姻期間中に形成された部分は共有財産に含まれると考えられています。
退職金については、勤続年数に応じて積み立てられるため、離婚時点での勤務期間を基準にわけて計算するケースが多いです。
たとえば、20年勤続のうち10年が婚姻期間であれば、その部分に相当する退職金が分与対象となります。
年金についても、厚生年金や共済年金は「年金分割制度」により、婚姻期間中の記録を分け合うことが可能です。
特に専業主婦(夫)の場合、自ら年金保険料を納めていなくても、配偶者の記録を分割できるため老後の生活保障につながります。
財産隠しを防ぐための調査ポイント
離婚に際してよく問題となるのが、財産隠しです。
預金を引き出して現金化したり、親族名義に資産を移すなど、不正な手段で共有財産を隠すケースがあります。
これを防ぐには、日常的に家計の流れを把握し、不自然な出金や資産移動がないかをチェックすることとあわせて、通帳のコピーや領収書を保存しておくことも有効です。
また、調停や裁判の場では、金融機関や勤務先に対して資料の提出を求める手段もあります。
財産隠しが判明した場合、裁判所はその分を考慮して分与割合を調整することがあります。さらに、専門家に調査を依頼することで、表面化しにくい資産を発見できることもあります。
共有財産を守るための予防策
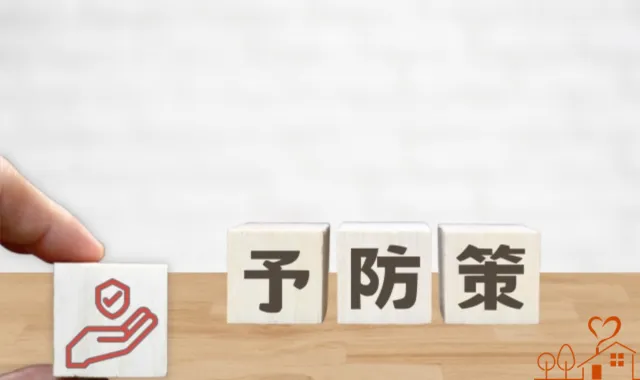
夫婦として生活する場合、または離婚時のトラブルを防ぐために、共有財産は適切に管理されなければなりません。
ここでは、共有財産を守るための対策について詳しく解説します。
婚姻契約(夫婦財産契約)を結ぶメリット
夫婦が結婚前に取り決めを行う「婚姻契約(夫婦財産契約)」は、共有財産を守る有効な手段です。
これは夫婦間で財産の帰属や管理方法を事前に定めるものです。
公正証書にすることで法的効力を持ちます。
たとえば、婚姻後に得た財産を各自の特有財産とする、あるいは収入の一定割合を共有財産とするなど、柔軟な取り決めが可能です。
これにより、離婚時の財産分与トラブルを未然に防ぎ、透明性のある財産管理が実現できます。
日本ではあまり普及していませんが、婚姻契約を結ぶことで、夫婦間の信頼関係を強化し、不要な争いを避けられるという大きなメリットがあります。
定期的な財産リストの作成と共有の重要性
夫婦が財産を正しく把握し合うためには、定期的に財産リストを作成し、互いに共有するのがおすすめです。
預貯金、不動産、株式、保険、退職金などを一覧化することで、家庭の資産状況が一目で分かり、将来の計画にも役立ちます。
特に、いざ離婚や相続といった事態が起きた際、財産の全貌を把握していないと不利益を被る恐れがあります。
リスト化を習慣化すれば、不自然な財産移動や浪費の兆候にも早く気づけるため、財産隠しの予防にもつながります。
また、夫婦間で情報をオープンにすることは信頼関係の強化にも寄与するでしょう。
贈与や相続時に特有財産を明確化する方法
婚姻中に一方が贈与や相続によって得た財産は特有財産として扱われ、離婚時の分与対象には含まれません。
しかし、共有財産と混在すると判断が難しくなることがあります。
たとえば、相続で得た資金を共有口座に入れてしまうと、共有財産とみなされるリスクがあります。
これを避けるためには、特有財産を明確に区分し、専用の口座で管理することが有効です。
また、不動産を相続した場合は登記簿に単独名義で登記しておくことで特有財産であることを証明できます。
さらに、贈与税や相続税の申告書も、特有財産を裏付ける資料として重要です。
特有財産を計画的に管理することで、自身の資産を確実に守れるでしょう。
税務対策としての財産管理の工夫
共有財産の管理には、税務上の工夫も欠かせません。
たとえば、夫婦が共同で不動産を所有する場合、登記上の持分割合を調整することで将来の相続税や贈与税の負担を軽減できることがあります。
また、教育資金や住宅取得資金の特例を活用することで、贈与税を抑えながら資産を有効に活用可能です。
さらに、金融資産についても夫婦間で分散して管理することで、課税所得の偏りを避けられます。
財産分与に際しても、税金が発生するケースがあり、特に不動産や株式を移転する場合には譲渡所得税や登録免許税が問題となることがあります。
事前に税務の観点から最適な方法を検討しておけば、不要なコストを削減し、資産を効率的に守れるでしょう。
専門家に相談する必要性

共有財産の調査や適切な分与については、個人ですべてを対応するのは難しい場合があります。
専門家に相談して、適切に対応できるようにするのがおすすめです。
ここでは、専門家に相談する必要性について詳しく解説します。
財産分与や共有財産の判断に専門家が関わるメリット
財産分与は法律や税務、不動産評価など複雑な要素が絡み合うため、専門家に対応してもらうことをおすすめします。
弁護士は法的観点から共有財産の範囲や分与割合について助言し、調停や裁判での代理人として依頼者をサポートします。
税理士は財産分与に伴う税負担の最小化を提案し、司法書士は不動産の名義変更や登記手続きを担います。
こうした専門家が関わることで、依頼者は法的リスクを避けつつ、適切かつ公平な分与を実現できます。
また、相手方との交渉においても専門家の存在は大きな抑止力となり、無理な要求を防ぐ効果があります。
弁護士に依頼する際の費用と相談の流れ
弁護士に財産分与を依頼する場合、費用は相談料、着手金、成功報酬などで構成されます。
正式に依頼すると着手金が発生し、数十万円程度となることが一般的です。
成果に応じて報酬金が加算されるケースもあります。
相談の流れとしては、まず財産状況や離婚条件についてのヒアリングが行われ、その後、調停や裁判に向けた方針を立てます。
弁護士は証拠収集や書類作成、裁判所での主張立証を代理し、依頼者の負担を大幅に軽減してくれます。
費用は決して安くはありませんが、不利な分与を避けることや精神的負担を軽くする効果を考えれば、依頼する価値は十分にあります。
複雑な財産分与案件では、早期の相談がおすすめです。
司法書士や税理士がサポートできる領域
司法書士や税理士も、財産分与の重要なサポート役となります。
司法書士は不動産の名義変更や登記申請の手続きを代行でき、財産分与の合意を確実に法的に反映させる役割を担います。
一方、税理士は財産分与に伴う税金の計算や申告をサポートします。
特に不動産や株式を分与する場合、譲渡所得税や登録免許税、贈与税が関わるため、税理士の助言が不可欠です。
また、将来的な相続税のシミュレーションや節税対策も提案できるため、財産管理の長期的な視点を持てるようになります。
弁護士と連携して依頼すれば、法律・税務・登記を総合的にカバーでき、適切な財産分与を進めつつ、トラブルを未然に防げるでしょう。
探偵に依頼することで把握できる共有財産の実態
離婚時の財産分与において、相手が財産を隠しているケースは少なくありません。
銀行口座や証券口座、不動産、保険契約などは名義や所在が不明瞭になりやすく、片方が一方的に管理していると発覚しにくいのが実情です。
こうした場合に有効なのが、探偵への依頼です。
探偵は独自の調査力を用い、金融機関の利用状況、不動産の登記情報、企業との関係性などを調べ上げ、表に出てきていない財産を特定します。
たとえば、普段使っていない銀行口座に多額の預金があったり、家族に黙って購入した不動産や投資商品が見つかるケースもあります。
これらの情報は、弁護士を通じて裁判所に証拠として提出することで、正当な分与請求の根拠になります。
探偵に依頼することで、隠された財産を可視化し、公平な財産分与を実現する道筋を確保できるのです。
夫婦の共有財産を正しく理解し、トラブルを未然に防ぐ
共有財産を把握することで、トラブルの回避や離婚後の生活の安定につながります。
本記事を参考に、どのような財産が共有財産になるのか理解したうえで、普段から共有財産を適切に管理しておくことが重要です。
また、相手の隠し財産について調査が必要な場合は、名古屋東海ファミリー探偵社にご相談ください。
独自の調査ノウハウを駆使して、個人では発見できない隠し財産の調査が可能です。