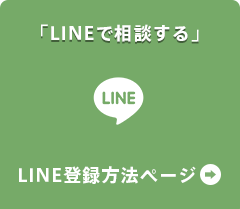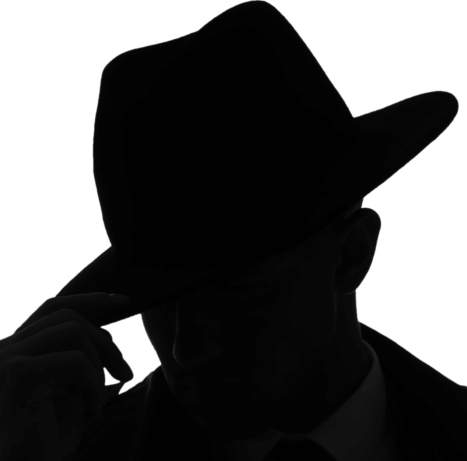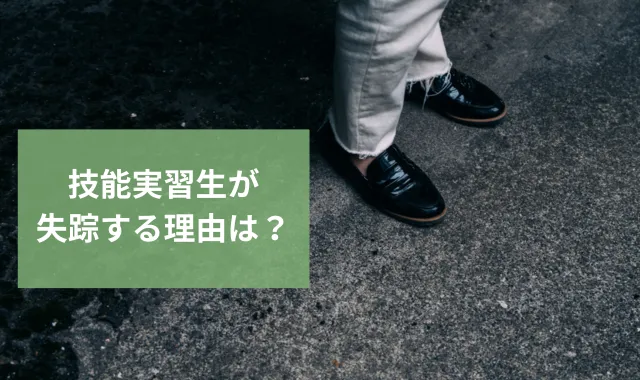
「実習生が突然いなくなった」
「しばらく連絡が取れない」
技能実習制度に携わる企業担当者のなかには、こうした状況に直面した経験がある方も少なくないでしょう。
技能実習生の失踪は企業の労務体制や社会的信用に影響を及ぼす深刻な問題であり、制度全体の信頼にもかかわる重大なリスクです。
とくに近年は失踪者数が増加傾向にあり、「自社は大丈夫」と言い切れない状況になりつつあります。
本記事では技能実習生が失踪に至る主な理由や背景を詳しく解説し、企業として取るべき事前対策と、万が一失踪が発生した際の適切な対応方法についてまとめました。
制度を正しく運用し、実習生との信頼関係を築くためにも、「なぜ失踪が起きるのか」「どう対応すべきか」を知ることが、企業担当者にとって今や不可欠です。
ぜひ最後までご覧いただき、実務にお役立てください。
目次
技能実習生の失踪の実態

法務省出入国在留管理庁が2024年に公表した資料によると、2023年の外国人技能実習生の失踪者数は9,753人にのぼり、過去最多を記録しました。
一方で、失踪者の割合は全体の1.9%と、前年とほぼ横ばいの水準で推移しています。
|
令和元年 |
令和2年 |
令和3年 |
令和4年 |
令和5年 |
|
|
技能実習生数 |
517,358 |
495,082 |
406,946 |
463,188 |
509,373 |
|
失踪者数 |
8,796 |
5,885 |
7,167 |
9,006 |
9,753 |
|
失踪者の割合 |
1.7% |
1.2% |
1.8% |
1.9% |
1.9% |
割合自体は大きく変化していないものの、技能実習制度の拡大とともに外国人労働者の母数が増加している現状を考えると、実数の増加は看過できません。
とくに建設や製造などの分野では、技能実習生の存在が不可欠になっている企業も多く、1人の失踪が職場全体の業務に大きな支障をきたす可能性があります。
さらに、失踪によって企業の信用や制度上の優遇措置に影響が出るケースもあり、企業にとって深刻なリスクとなる事案であることは間違いありません。
今後も外国人材の受け入れが加速するなか、失踪問題への対策は企業・団体レベルでの重要課題として、引き続き注視することが必要です。
技能実習生が失踪する理由
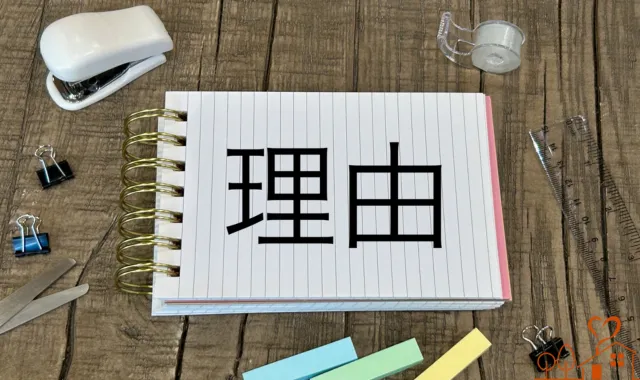
技能実習生の失踪を防ぐためには、理由を理解することが大切です。
ここからは、技能実習生が失踪する理由を解説します。
現場での暴力や暴言・差別
技能実習生の失踪理由の一つとして、職場内での暴力や暴言、差別的な扱いを受ける点があげられます。
実際に、日本語が話せないことや見た目との違いを理由に、技能実習生が叩かれたり差別的な言葉を投げかけられたりするケースがあるのです。
「特定非営利活動法人 移住者と連帯する全国ネットワーク」が発表している「外国人労働者が遭遇するパワーハラスメント ハラスメント(レイシャルハラスメント)事例」では次のようなハラスメントの事実が報告されています。
- 日本語が通じないから体で指導すると日常的に工具で叩かれる
- 「国へ帰れ」などの暴言を浴びせられうつ病を発症した
- 施設利用者から身体的な特徴に対して差別的な呼び方をされる
また、身体的な暴力や差別だけでなく、宗教に対する差別から失踪につながる場合もあります。
例えば、イスラム教徒の技能実習生に豚肉を無理やり食べさせたり、ラマダンやクリスマスなど宗教上大切な日を無視した勤務命令を出したりすることは、明確な差別行為です。
このような暴行や暴言、文化や宗教への無理解がハラスメントとして現場に蔓延している場合、実習生は自らの尊厳を守るために失踪という手段を選んでしまいます。
契約に対する認識の不一致
技能実習生の失踪には、契約内容に対する認識のズレが背景にあることも少なくありません。
とくに日本語が十分に理解できない実習生に対して、契約書を日本語だけで提示し、内容の説明が不十分なまま契約させてしまうケースが問題視されています。
その結果、「思っていたよりも給与が低い」「勤務時間が長い」「休みが取れない」といった不満が後から生じ、労働環境への不信感が積み重なって失踪につながってしまうのです。
さらに、稀ではありますが、外国人労働者であることを理由に、残業代の未払いなどの不正行為を行なう企業も存在します。
こうした不正は法令違反にあたるだけでなく、企業の信頼や制度そのものの健全性を損なう要因となり得ます。
企業としては「言葉の壁」を理由に契約の説明責任を軽視することなく、誠実な対応を徹底する姿勢が必要です。
人間関係や言葉の問題による孤立
技能実習生が失踪してしまう理由には、日本語でのコミュニケーションがうまく取れず、職場で孤立してしまうこともあげられます。
言葉の壁によって意思疎通が困難になると、実習生は周囲との関係構築をためらうようになり、次第に孤独感や疎外感を深めてしまうのです。
例えば、「話しかけても伝わらないのでは」「迷惑をかけてしまうのでは」といった不安から、実習生自身が積極的な関わりを避けてしまうことがあります。
とくに母国では家族や友人に囲まれていた若者にとって、異国での孤独は強いストレスとなり、精神的に追い詰められた結果、失踪という手段を選んでしまいます。
悪質ブローカーによる借金に困窮
技能実習生の失踪には、母国での渡日前準備段階からすでにトラブルが始まっているケースもあります。
その一因として挙げられるのが、悪質なブローカーによる高額な紹介料や詐欺的な契約です。
実習生の多くは、日本での就業前に母国の日本語学校などで約半年間の語学教育を受けることが一般的です。
その際、学費や渡航費を借金して工面する実習生も多く、日本で働きながら少しずつ返済していくという計画で来日します。
しかし一部では、悪質ブローカーが「日本に行けばすぐに高収入が得られる」と虚偽の情報を与え、相場を超える紹介料や不当な手数料を請求することがあります。
その結果、実習先で真面目に働いても返済が追いつかず、生活が破綻寸前に陥るケースもあるのです。
借金の重圧に耐えかねた実習生は、より高収入の職を求めて正規の実習先から逃げ出し、不法就労に手を染めるケースもあります。
実習生の私生活上の問題
技能実習生の失踪は、実習生本人の素行や私生活上の問題が原因となっているケースも存在します。
ごく稀ではありますが、実習生が日本での労働生活に嫌気が差し、自ら職場を離れてしまう事例も少なからず存在するのです。
さらに、失踪後に犯罪に関与してしまう実習生も一部存在しており、社会問題化しています。
例えば、技能実習生として来日していた外国人が、農作物の窃盗事件や強盗殺人事件などの重大な刑事事件を犯す例もあります。
このような事例はあくまで例外的なケースですが、制度全体の信頼性や外国人労働者に対する偏見を助長する要因にもなり得るため、決して看過できない問題です。
技能実習生を失踪させた企業へのペナルティ

技能実習生が失踪した場合、実習生のみならず企業にペナルティが課せられるケースもあります。
ここでは、技能実習生を失踪させた企業に与えられるペナルティを解説します。
失踪数が多いと受け入れ停止になる
技能実習生の失踪が相次ぐ企業は、新たな実習生の受け入れを停止されることがあります。
これは、失踪の多さが労働環境の深刻な問題を示していると判断されるためです。
出入国在留管理庁などの調査で、劣悪な労働条件やハラスメントの常態化が明らかになれば、受け入れ停止に加え、企業としての信用にも大きな打撃を受ける恐れがあります。
実習生の受け入れ停止は人手不足を招くだけでなく、社会的な信頼の低下にもつながる重大なリスクです。
優良認定が取り消されて信用が落ちる
技能実習生を失踪させてしまうことで、技能実習制度の優良認定が取り消される可能性もあります。
技能実習制度には「優良な実習実施者」として認定される優良認定制度が設けられています。
優良認定を受けた企業は、受け入れ人数の上限緩和や実習期間の延長など、制度上の優遇措置を受けることが可能です。
しかし、技能実習生の失踪が多発していたり、労働環境や管理体制に重大な問題が認められたりする場合には、優良認定が取り消されることがあります。
事実、優良認定の基準には以下の点が重視されるため、失踪によって要件を満たせなくなる可能性が高いです。
- 直近過去3年以内の改善命令の実績、失踪の割合
- 直近過去3年以内に実習実施者に責めのある失踪の有無
対外的な取引先や地域社会との信頼関係を重視する企業にとって、優良認定の喪失は大きなマイナスイメージとなりかねません。
ペナルティを受けないためにも、企業は技能実習生を失踪させないような対策が必要です。
技能実習生が失踪した際に必要な対応

技能実習生が失踪してしまった場合には、早急な対応が欠かせません。
ここでは、技能実習生が失踪した際に企業が取るべき対応を紹介します。
管理団体に連絡する
技能実習生が失踪したことに気づいた場合、まず最初に行なうべき対応は、速やかに管理団体へ連絡することです。
管理団体は企業と実習生の間に立ち、制度の運営や実習の監督を担っている組織であり、失踪時の対応にも重要な役割を果たします。
連絡を受けた管理団体は実習生の母国にある送出機関や家族への連絡を通じて、状況の確認や情報収集などを迅速に行います。
実習生の過去の様子や人間関係、行動パターンなども把握しているため、所在確認の手がかりとなる情報を集めることが可能です。
対応が遅れると、失踪実習生が違法就労や犯罪に巻き込まれるリスクが高まります。
また、企業側の管理責任が問われる可能性もあるため、失踪に気づいたら即座に管理団体へ報告することが基本対応の第一歩です。
警察で行方不明者届を出す
技能実習生が失踪し、管理団体と連携しても所在が特定できない場合は、速やかに警察へ行方不明者届を提出することが重要です。
単なる無断外出ではなく、一定時間を経ても連絡が取れず、行方がわからない状況が続く場合には、事件や事故に巻き込まれている可能性も否定できません。
警察への届け出により、行方不明者としての捜索活動が開始され、公共機関としての権限を持った調査が進められます。
また、万が一不審な第三者による連れ去りや、人身売買などの犯罪が関与していた場合にも、早期対応が事態の深刻化を防ぐ鍵となります。
警察への相談は、企業としての誠実な対応を示すものであり、法的・社会的にも正当な手続きです。
失踪が判明したら早急に管理団体と協議し、必要に応じて迷わず警察への届け出を行なうことが、実習生保護と企業防衛の両面で不可欠です。
技能実習実施困難届出を提出する
技能実習生が失踪し、一定期間が経過しても発見されず、就業の継続が困難と判断された場合には、外国人技能実習機構へ「技能実習実施困難届出書」を提出する必要があります。
とくに失踪に関しては、企業や管理団体が誠実に対応していたかが重視されるため、届出には事実経過を正確かつ詳細に記載することが重要です。
虚偽の報告や提出の遅れは、企業の信頼を損なうだけでなく、今後の実習生受け入れに支障をきたす恐れがあります。
届出後、外国人技能実習機構は必要に応じて事情聴取や監査を実施し、制度の適正な運用状況を確認します。
企業としては責任を問われないためにも、失踪時の対応記録や書類を適切に保管し、説明責任を果たせる体制を整えておくことが大切です。
技能実習生を退職させる
技能実習生が長期間失踪し、実習の再開が見込めない場合は、企業側で正式な退職手続きを行なう必要があります。
失踪という事情があっても、雇用関係を曖昧なまま放置すると、労務管理上のリスクが生じる恐れがあります。
社会保険や労働保険、給与台帳などの記録上も、在籍状況を明確にするために適切な処理が必要です。
具体的に必要な手続きは、以下のとおりです。
- 退職届または退職に関する社内文書の作成
- 雇用保険・健康保険・厚生年金などの脱退手続き
退職処理後も、対応記録を保管し、管理団体や関係機関からの照会に備える体制を整えておくことが望まれます。
失踪した実習生の発見に探偵がおすすめな理由
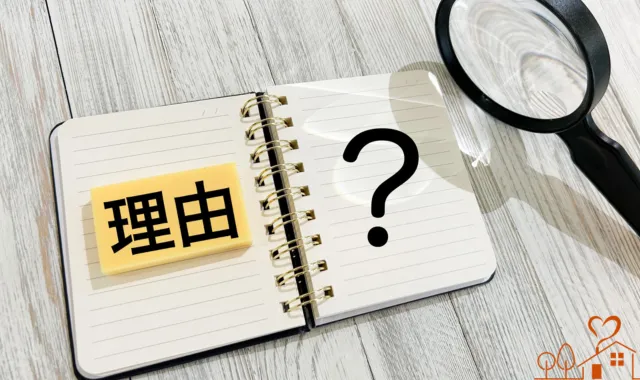
技能実習生が失踪してしまった場合は、さまざまな対応が必要になります。
しかし、最も重要なことは失踪した実習生を発見することです。
実習生が発見されれば、実習生自身の身の安全を確保できるうえ、違法労働など犯罪に手を染めてしまう可能性を下げられます。
失踪した実習生を捜索するには、探偵の利用がおすすめです。
ここでは失踪した技能実習生の捜索に、探偵への依頼がおすすめな理由を解説します。
海外を含めた調査が可能
失踪した実習生の発見に探偵がおすすめな理由として、専門スキルを用いて海外を含めた調査ができる点があげられます。
技能実習生の失踪後、その行き先は日本国内にとどまらず、ブローカーの手引きで母国や第三国へ渡航している可能性もあります。
このような広域・複雑なケースにおいては、企業や管理団体による調査だけでは限界があるのが現実です。
探偵は、長年の経験に基づく高度な情報収集力、張り込み・聞き込み調査などの専門技術を駆使し、実習生の足取りを追うことが可能です。
さらに、海外とのネットワークを活用した調査体制を持つ探偵であれば、国外への渡航や外国人ブローカーの関与が疑われるケースにも対応できます。
こうした専門スキルによって、失踪実習生の早期発見や、今後の再発防止に向けた情報収集ができるため、探偵の活用は有効な選択肢といえるでしょう。
国内法と国際法を犯すリスクの低減
探偵に調査を依頼することで、企業や管理団体が国内法や国際法を誤って犯してしまうリスクを回避できます。
技能実習生が失踪した際、自力での情報収集や独自の捜索を試みる企業もあります。
しかし、法的な知識がないまま調査を始めると、無許可での個人情報の取得や不適切な聞き込みなど、違法な調査行為を行ってしまうリスクが高いです。
また、実習生の行方が海外に及ぶ場合には、相手国の法律や国際条約に違反するリスクも否定できません。
一方、正規に届け出を行っている探偵は、調査に関する法令を熟知しており、適法な手順で証拠や情報を収集します。
必要に応じて弁護士と連携しながら、国内外の法的リスクを回避しつつ調査を進めることが可能なため、知らずして違法行為を行なう心配がありません。
探偵の活用は法的リスクを最小限に抑えながら確実な調査を進めるうえで、非常に理にかなった選択肢といえるでしょう。
再発防止策のアドバイスや監査支援
探偵は失踪の原因を分析し、企業や管理団体に対して再発防止に向けた具体的な対策や内部監査の支援を行なうことができます。
技能実習生が失踪した場合、単に所在を特定するだけでは根本的な解決にはなりません。
重要なのは、失踪が起きた背景や職場環境の構造的な問題を明らかにし、再発を防ぐための実効性ある対策を講じることです。
探偵は調査結果やこれまでの経験をもとに、次のような実践的アドバイスを提供できます。
- 労務管理上の改善点の洗い出し
- 契約手続きや説明体制の見直し
- コミュニケーション支援策の提案
- ハラスメント防止研修の導入
- 管理体制に関する監査項目の策定
さらに、調査を通じて得られた知見は、監理団体や送出機関との連携強化、社内教育の改善にも活用可能です。
こうした取組みは、実習生にとって安心できる職場環境づくりにつながり、企業にとっても信頼回復と制度継続に役立ちます。
技能実習生を失踪させないための対策法

技能実習生が失踪した際は、早急な対応が欠かせません。
しかし、最も重要なことは技能実習生を失踪させないことです。
ここでは技能実習生を失踪させない対策法を解説します。
契約内容を明確に説明する
技能実習生の失踪を防ぐうえで最も基本的かつ重要な対策は、労働契約の内容を明確に説明し、相互に理解を得たうえで合意することです。
労働契約において企業と実習生との間に齟齬が起きないようにするには、日本語だけでなく、実習生の母国語でも契約書を作成することが不可欠です。
加えて、内容の読み合わせを通訳付きで行い、本人の理解度を確認したうえで契約を結ぶ姿勢が求められます。
また、契約内容の説明は一度きりで終わるものではなく、就業後も定期的に内容の再確認や疑問点のヒアリングを行なうことが望まれます。
実習期間中に制度や手続きが変わる場合もあるため、情報のアップデートを随時伝える努力が、信頼関係を維持するうえでも重要です。
文化への理解やハラスメントの予防
実習生の失踪を防ぐためには職場全体で異文化理解を深め、ハラスメントを未然に防ぐ体制を整えることが不可欠です。
技能実習生は多くの場合、日本とは異なる宗教・価値観・生活習慣を持つ国から来日しています。
そのため、何気ない一言や対応が、実習生にとっては差別や侮辱と受け取られることもあるのです。
例えば、宗教的な食事制限を軽視したり、信仰行事への配慮がないまま業務を強制することは、深刻な精神的苦痛を与える原因となります。
次のような対策を行って、無意識の偏見や慣習の違いによる摩擦を防ぐ対策が必要です。
- 多文化共生に関する社内研修の実施
- 宗教的な配慮やNG事項の共有リスト作成
- ハラスメント発生時の相談窓口や報告体制の明確化
職場全体での理解と配慮が、実習生の安心感と信頼を築き、結果として長期的かつ安定した就業の実現につながります。
「こうかんノート」を活用してコミュニケーションを強化
技能実習生の孤立や誤解を防ぎ、失踪を未然に防ぐためには、こうかんノートを活用した定期的なコミュニケーションの機会を設けることが効果的です。
「こうかんノート」とは、実習生と企業担当者がノート上でやり取りを交わすツールであり、出入国在留管理庁も活用を推奨しています。
言語の壁や対面では言いづらいことも、ノートという形式なら気軽に書けるという利点があります。
実際にこうかんノートを通じて、以下のような事柄を共有して実習生が抱える小さなサインを見逃さずに対応することが可能です。
- 業務に関する疑問点や不安の共有
- 体調や生活環境の変化に関する気づき
- 労働時間・休日・人間関係などに関する悩みの早期発見
また、企業側にとっても、実習生との信頼関係を築きやすくなるうえ、適切な記録を残すことで監査や万が一のトラブル対応にも活用できます。
もちろん、ノートのやり取りは単なる連絡事項の記載ではなく、温かみのある言葉での交流が、実習生の安心感や帰属意識を育てる大切な機会となるでしょう。
こうかんノートのような伝え合える仕組みの導入が、実習生の勤労を保護し、制度の持続と企業の信頼性獲得につながります。
技能実習生の失踪に関するよくある質問

最後に技能実習生の失踪に関するよくある質問を紹介します。
技能実習生の失踪は入管法違反にあたる?
はい、技能実習生が失踪し、許可された実習先を離れて無断で生活・就労を行なうことは、入管法違反に該当します。
技能実習制度は、あくまで研修目的での在留を前提とした在留資格のもとで運用されており、実習計画に基づいた活動が義務づけられています。
そのため、実習生が実習先から逃げ出して別の職場で働いたり、所在不明となったりする場合には、在留資格に基づかない活動とみなされる可能性があります。
失踪した技能実習生は強制送還させられる?
はい、失踪した技能実習生は、原則として不法残留者・不法就労者とみなされ、強制送還の対象です。
技能実習生は、本来の実習先での活動を前提として在留資格を付与されています。
よって、無断で実習を放棄し、所在不明のまま他の場所で働くことは「資格外活動」に該当し、入管法違反となります。
そのため、警察や入国在留管理局によって発見された場合には、在留資格の取り消し処分を受け、退去強制手続きが進められることになります。
また、強制送還後には原則5年間の上陸拒否期間が設けられ、その間は日本に再入国できません。
過去に不法残留歴や犯罪歴がある場合は、さらに長期の上陸拒否措置が取られることもあります。
一方で、人道的な理由ややむを得ない事情が認められる場合には、例外的に個別に審査が行われることもあります。
失踪した技能実習生のその後はどこへ行く?
失踪した技能実習生の多くは、都市部での不法就労や他の外国人ネットワークに身を寄せて潜伏しているケースが多く、所在の特定は非常に困難です。
実習先から姿を消した実習生が、そのまま帰国することは稀で、より高収入を得られる仕事を求めて都市部へ移動します。
多くの場合は、建設現場や飲食業などの現場で違法に働いているケースが報告されています。
実際に、失踪した実習生の発見率は非常に低く、見つかるまでに数ヵ月から数年を要するケースも多いです。
結果として、受け入れ企業や監理団体にとっても長期的な負担となり、制度全体への信頼にも影響を及ぼします。
失踪の未然防止とともに、発生時の迅速な対応と追跡体制の整備が、今後ますます重要になるといえるでしょう。
技能実習生の失踪には事前の対策が重要

技能実習生の失踪は、企業にとっても制度にとっても大きなリスクです。
対応が後手になると、信頼の失墜や受け入れ停止といった深刻な影響を招きかねません。
だからこそ重要なのが、契約内容の明確化や文化への理解、日常的なコミュニケーションの強化など、失踪を防ぐための事前対策です。
万が一失踪が発生した場合でも、速やかな対応と探偵による専門的な調査支援を受けることで、被害とリスクを最小限に抑えられます。