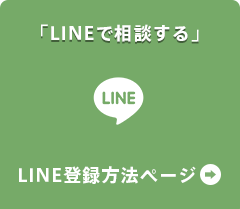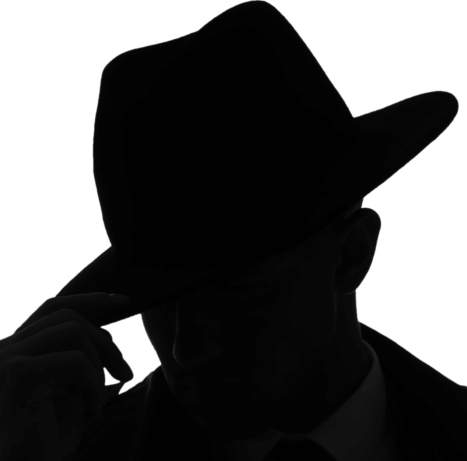被相続人が亡くなってから、正確な相続を実現するには、相続財産の調査が不可欠です。
しかし、個人で調査をするには限界があるほか、他の相続人が不信感を抱く場合もあり、困っている方もいるでしょう。
実際、分割協議や相続税申告の後に、隠された財産が発覚して、対応に追われるケースがあります。
そこで重要になるのが、相続の財産調査です。
専門家による財産調査により、相続額が大きくなったり、的確に相続放棄を選択することもできます。
今回は、相続の財産調査の基礎知識や調査の流れを解説します。
目次
相続における財産調査とは?

相続が起きたときに行う財産調査とは、どのようなことを調べるのか、詳しく解説していきます。
相続財産調査の定義と役割
相続財産調査とは、亡くなった方(被相続人)が遺した全ての財産を特定し、その内容や価値を正確に把握する調査のことです。
なお、相続財産調査では、プラスの財産(不動産や預貯金、株式など)だけでなく、借金などのマイナスの財産も調べます。
マイナスの財産が相続されると、相続人がその負担を抱えることになるため、キチンと把握する必要があります。
また、相続税の申告や納付額を正確に計算するためにも欠かせない調査といえます。
財産の内容を把握しないまま手続きを進めてしまうと、後になって隠れた借金が発覚したり、不正確な情報で相続税の申告をしてしまうというリスクに直面するためです。
調査を行わない場合に起こるトラブル事例
相続財産調査を怠ると、後々深刻なトラブルに発展する恐れがあります。
主に起こりやすいのが次のトラブルです。
- 遺産分割後に新たに財産が見つかるケース
- 遺産分割後に負債が見つかるケース
- 財産の全容が不明確な相続税を申告し、追徴課税や延滞税が課されるケース
遺産分割後に財産や負債が見つかれば、遺産分割協議のやり直しが必要になったり、相続人全員が負債の負担が必要になったりすることがあります。
また、財産の全容が不明確なまま相続税を申告すると、税務署から指摘を受け、追徴課税や延滞税が課されることになりかねません。
こうした事態を避けるためにも、相続開始後のできる限り早い段階で、網羅的な財産調査を行うことが極めて重要になります。
財産調査が必要になる典型的なケース
相続財産調査が必要となるのは、次のようなケースです。
配偶者や子どもが故人の財産状況を全く把握していない場合、どこにどのような財産があるのかを知るために、調査は必須となります。
兄弟姉妹や甥姪など、相続人の数が多いと、全員が納得する公平な遺産分割を目指すために、客観的な財産情報が不可欠となります。不透明な部分があると、相続人同士の不信感を生み、争いの原因にもつながりかねません。
プラスの財産だけでなくマイナスの財産も正確に把握しなければ、相続放棄や限定承認といった手続きの判断ができません。
財産状況が複雑であったり、相続人間で意見の対立が予想されたりする場合には、専門的な財産調査が必要です。
探偵に依頼するケースと弁護士・司法書士との違い
相続財産調査は、自分で進める方法のほか、弁護士や司法書士、探偵といった専門家に依頼する選択肢があります。
弁護士や司法書士は、法律の専門家として、法的手続きや相続に関するアドバイス、書類作成などを主に行います。
戸籍や住民票、登記簿謄本などの公的書類を調査する権限を持っており、主にプラスの財産、特に不動産や預貯金の調査が得意です。
探偵は、法律の枠を超えた広範な調査能力と情報収集力を持ち、公的記録には現れない「隠し財産」や「隠れた借金」の発見に強みがあります。
例えば、被相続人が内密に所有していた銀行口座や、家族に内緒で借り入れをしていた事実などが、探偵の調査によって明かされることがあります。
弁護士や司法書士が法的手続きの代行を得意とするのに対し、探偵は情報そのものを探り当てるプロフェッショナルといえるでしょう。
財産調査で判明する資産の種類と調査方法

財産調査では、文字通り被相続人が所有するさまざまな財産の種類が判明します。
どのような財産が見つかり、その財産を見つけるためにどのような調査が行われるのか、詳しく解説します。
預貯金・証券など金融資産の調査方法
預貯金や有価証券といった金融資産は、相続財産の中でも相続人に大きな影響を与える財産です。
これらの財産を調査するには、被相続人の自宅から通帳やキャッシュカード、銀行からの郵便物などを探し出し、取引のあった金融機関を特定します。
オンラインで取引を行っていた場合、紙の書類が存在しない場合があるため、故人が使用していたパソコンやスマートフォンの履歴から証券会社を特定する調査が必要です。
不動産や土地の権利関係を調べる方法
不動産や土地の調査は、相続財産調査の中でも特に手間がかかる調査です。
まず、故人が所有していた不動産の情報を得るために、自宅から不動産の権利証や固定資産税の納税通知書を探し出し、不動産の所在地や地番、家屋番号などを確認します。
これらの情報をもとに、法務局で「登記事項証明書(登記簿謄本)」を取得すれば、不動産の所有者や面積、担保権の有無などを公的に確認可能です。
また、不動産の正確な評価額を知るためには、市区町村役場で「固定資産評価証明書」を取得するのが一般的です。
固定資産税の計算に使われる評価額が記載されており、相続税を計算する際の基礎資料となります。
さらに、故人がどの不動産を所有していたか分からない場合は、市区町村役場で故人名義の全ての不動産が一覧で記載されている「名寄帳(なよせちょう)」を請求するケースもあります。
株式・投資信託・保険などの隠れ資産
株式や投資信託、生命保険、暗号資産のような、見つけにくい隠れ資産にも調査が行われます。
これらの資産は、通帳や権利証といった物理的な証拠が残りにくいケースがあり、故人のパソコンやスマートフォン、あるいはクラウドサービスの中に情報が残っている場合があります。
例えば、故人が利用していたメールアドレスやパスワードを把握できれば、オンライン上の証券口座や投資信託の契約情報を確認できる可能性があります。
また、生命保険は、故人宛に届いた保険会社からの郵便物や、給与明細から生命保険料が天引きされていないか確認したり、保険会社に生命保険契約紹介制度を利用して問い合わせたりすることで調査可能です。
さらに、故人が暗号資産を所有していた可能性がある場合、取引所からのメールや、ウォレットアプリの履歴などを丹念に探さなければなりません。
隠れ資産は、自己調査だけでは発見が困難な場合が多いため、必要に応じて専門家の協力を得ることを検討すべきでしょう。
借金やローンなど負の財産の洗い出し
プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多ければ、相続放棄や限定承認を検討する必要が出てきます。
負の財産を調べるためには、被相続人の自宅に届いた督促状や請求書、ローン返済の明細書などを探し出します。
また、銀行や消費者金融からの借入があるかどうかは、故人の信用情報を開示請求すれば、ある程度把握可能です。
住宅ローンについては、自宅の登記簿謄本を確認して、抵当権の設定の有無を確認できます。
連帯保証人になっていた場合も負の財産となるため、保証契約書などがないか確認されます。
負の財産は、放置すると相続人に大きな負担を強いることになるため、プラスの財産と同様に丁寧な調査が行われます。
相続財産調査を行うタイミングと流れ

相続財産調査は、どのタイミングで行われるのでしょうか。
ここでは、相続財産調査が実施されるタイミングと流れについて解説していきます。
被相続人が亡くなった直後に確認すべきこと
相続財産調査は、被相続人が亡くなった直後から迅速に着手することが重要です。
調査の初期段階でチェックされるのは、主に以下の通りです。
- 現金
- 預金通帳
- 印鑑
- 年金手帳
- 保険証券
- 権利証
- 銀行や証券会社の取引明細書
- クレジットカードの利用明細書
- 税金の納付書
- 故人のパソコンやスマートフォン
まず、自宅の貴重品や書類が保管されている場所を確認し、現金や預金通帳、印鑑、年金手帳、保険証券、権利証などを探します。
これらの書類は、故人の財産状況を把握する上で重要な手がかりとなるためです。
また、故人宛に届く郵便物も重要な情報源で、銀行や証券会社からの取引明細書、クレジットカードの利用明細、税金の納付書などは、金融機関や負債の存在を明らかにしてくれます。
特に、クレジットカードの明細からは、故人が利用していたサービスや、未払いの債務を特定するヒントが得られることが多いです。
そして、故人のパソコンやスマートフォンのメールの送受信履歴や、ブラウザの閲覧履歴からは、オンライン上の口座や取引情報を発見できる可能性があります。
これらの初動調査で得られた情報を基に、財産調査の全体像を徐々に組み立てられます。
相続放棄や限定承認の期限との関係
相続財産調査は、相続放棄や限定承認の期限と密接に関係します。
日本の民法では、相続放棄または限定承認を希望する場合、自己のために相続が開始したことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出なければいけないためです。
そのため、この3ヶ月という期間は、プラスの財産よりもマイナスの財産(借金など)が多いかどうかを判断するために、財産調査を行うための重要な期間となります。
この期間内に財産の全容が把握できないまま期限を過ぎてしまうと、原則として単純承認したとみなされ、たとえ多額の借金があったとしても、その全ての相続が求められます。
借金の存在が疑われるような場合には、迅速に財産調査を進め、3ヶ月の期限内に相続放棄か限定承認か、または単純承認かを選択できるようにしなければなりません。
調査完了から相続手続きまでの流れ
相続財産調査が完了し、財産の全容が明らかになったら、具体的な相続手続きへと進みます。
まず、財産目録を作成し、相続人全員で遺産分割協議を行いますが、その際、調査によって判明した全ての財産を一覧にした資料が役立ちます。
協議で全員の合意が得られたら、「遺産分割協議書」を作成し、全員が署名捺印します。
この遺産分割協議書は、不動産の登記手続きや預貯金の解約、名義変更を行う際に必要となる重要な書類です。
また、相続した財産が一定額を超える場合には、相続税の申告が必要です。
相続税の申告と納付は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に行う必要があり、財産調査で得られた情報に基づいて、税理士と協力して正確な相続税額を計算し、申告書を作成します。
これらの手続きをスムーズに進めるためには、調査段階で作成した財産リストや、取得した公的書類をきちんと整理しておくことが大切になります。
自分でできる相続財産調査の方法

相続財産調査は、専門家しか行えないものではありません。
被相続人の親族であれば、個人で行うことも可能です。
ここでは、自分でできる相続財産調査の方法について解説します。
通帳・印鑑・郵便物から分かる情報
相続財産調査を自分で行う場合、被相続人の自宅にある身の回り品を丁寧に探すことから始めましょう。
以下のポイントを探してみてください。
- 故人の使っていた財布
- タンス、机の引き出し
- 書斎やリビングの棚
それぞれの場所で、金融機関と取引をしていた手がかりがないかチェックしましょう。
- 通帳
- キャッシュカード
- 銀行からの郵便物
故人宛に届いた郵便物の中に、消費者金融からの督促状や、クレジットカード会社からの利用明細が含まれていれば、借金の存在を疑うきっかけにもなるでしょう。
不動産登記簿や固定資産税通知書の確認
相続財産の中でも大きな割合を占めることが多いのが不動産です。
故人が所有していた不動産の有無を調べるには、自宅に保管されている不動産の権利証(登記済証または登記識別情報通知書)や、毎年春先に届く固定資産税の納税通知書を探しましょう。
これらの書類が見つかれば、そこに記載されている情報をもとに、その不動産が故人名義であることを確認できます。
また、正確な不動産の情報を得るためには、既出の通り、法務局で登記事項証明書を、市区町村役場にて固定資産評価証明書や名寄帳などを取得したりします。
特に名寄帳は、同一人物が所有している全ての不動産が一覧になっており、不動産財産の見落としを防ぐうえで有効な書類となります。
クレジットカード・ローン明細の洗い出し
マイナスの財産、特に借金や未払い金の存在を自分で調べるには、クレジットカードの明細やローン契約書を洗い出します。
故人の自宅に届くクレジットカードの利用明細書をすべて確認しましょう。
明細書には、毎月の支払額や利用したお店、サービスが記載されており、未払い金がある場合はその金額が明確に示されています。
また、故人の財布や机の中から、クレジットカードの契約書や、ローンを組んだ際の契約書類などがないか、探してみてください。
これらの書類が見つかれば、借入先の金融機関や、借入額、返済状況などを具体的に把握可能です。
さらに、もし故人のパソコンやスマートフォンを操作できる状況であれば、メールの受信履歴から「返済のご案内」や「支払いが遅延しています」といった件名のメールを探してみるのも有効でしょう。
探偵に依頼する相続財産調査のメリット

相続財産調査を外部に依頼したい場合の選択肢の一つが探偵です。
探偵に相続財産調査を依頼するメリットは次の通りです。
金融機関をまたいだ広範な調査が可能
探偵に相続財産調査を依頼する大きなメリットは、金融機関を横断した広範な調査が可能な点です。
相続人自身が財産調査を行う場合、故人の取引銀行や証券会社を特定することから始めなければならず、見当違いの金融機関に問い合わせる手間が発生することがあります。
また、被相続人が複数の銀行に口座を持っていたり、オンライン上の証券会社を利用していたりすると、全ての金融機関を網羅的に調べるのは難しいといえるでしょう。
探偵に調査を依頼した場合、長年の経験と独自のネットワークを活かし、発見しづらい金融機関の情報を効率的に収集できます。
探偵の持つ専門的な情報収集能力は、相続財産の全容を正確に把握したいと考える人にとって、心強い味方となるでしょう。
相続人同士で不信感を抱くことなく調査できる
相続財産調査は、相続人同士の関係にヒビを入れるきっかけになりかねません。
特に、相続人の一人が代表して調査を進める場合、他の相続人から「財産を隠しているのではないか」「自分に有利になるように調査しているのではないか」といった疑いの目を向けられるリスクがあります。
こうした不信感は、その後の遺産分割協議を円滑に進める上で大きな障害となるかもしれません。
探偵は、特定の相続人の味方をするわけではなく、客観的な立場から事実のみを追及するほか、調査結果は偏りのない客観的な報告書として提出されるため、相続人全員がその内容を信頼しやすくなります。
調査の透明性が確保され、相続人同士がお互いに疑心暗鬼になることを避け、円満な遺産分割協議へとつながる可能性が高まります。
財産調査をプロに任せることは、金銭的なメリットだけでなく、親族間の大切な関係を守る上でも大きな意味を持つといえるでしょう。
隠し財産や借金の発見精度が高い
探偵に相続財産調査を依頼するメリットとして、隠し財産や隠れた借金を発見する精度が高い点が挙げられます。
故人が家族に内緒で銀行口座を開設していたり、個人的な付き合いで借金をしていたりする場合、公的な書類だけでその存在を把握することは難しいものです。
探偵は、故人の行動履歴や交友関係、生活パターンなど、多角的な視点から情報を収集し、隠された事実を突き止めます。
例えば、故人が頻繁に訪れていた場所や、特定の人物とのやり取りなどを調査することで、通常の調査では見つからない手がかりを見つけられるケースがあります。
探偵ならではの調査手法によって、隠し財産や借金を明らかにし、相続全体に影響を与える重要な事実を発見できる可能性を秘めています。
法的手続きに役立つ客観的な証拠収集
探偵が行う相続財産調査は、情報収集だけではなく、その結果を法的手続きに役立つ客観的な証拠として提供してくれる点が大きなメリットです。
探偵は、調査で得た情報を詳細な調査報告書としてまとめ、クライアントに提出します。
報告書には、発見された財産の詳細(口座情報、残高、所在地など)や、負債の有無、そしてその証拠となる写真や書類のコピーなどが含まれています。
これらの情報は、その後の遺産分割協議や、万が一、相続人同士で訴訟に発展した場合の証拠として、有効に活用可能です。
特に、故人の隠し財産や負債をめぐって紛争が起こった際には、第三者である探偵が作成した客観的な報告書は、事態を解決に導く決定的な証拠となることがあります。
探偵に相続財産調査を依頼する流れ

本項では、相続財産調査を依頼する流れや依頼時に確認すべきポイントについて解説します。
初回相談で確認すべき内容
探偵に伝える内容や確認すべき内容は、主に次の通りです。
- 故人の氏名
- 故人が死亡した日
- 相続人の名前と親族関係
- 現時点で把握している財産の情報
- 探偵に調査を依頼した理由
- 調査費用や調査期間
現時点で把握している財産については「銀行の通帳は見つかったが、他の口座があるかもしれない」「不動産があるのは分かっているが、詳細な情報が不明」といった形で構いません。
また「隠し財産があるのではないかと疑っている」「相続人同士の関係が悪化していて、第三者の調査が必要だと感じている」など、探偵に調査を依頼したい理由を具体的に伝えると、探偵もより適切な調査プランを提案しやすくなります。
そして、重要なのが、調査費用や成功報酬の仕組み、調査期間について具体的に質問することです。
見積もり内容が明確で、納得できるまで丁寧に説明してくれる探偵事務所を選ぶことが、安心して依頼を進めるための鍵となります。
調査契約書のチェックポイント
初回相談を経て、探偵に正式に調査を依頼することになったら、調査契約書の内容を細かく確認してください。
特に、次のポイントが明確に記載されているかチェックしましょう。
- 調査目的と範囲
- 調査費用(着手金、成功報酬、追加費用発生の条件)
- 調査期間(開始日と終了予定日)
- 調査によって得られた情報の取り扱い方法
調査の目的と範囲は「故人の全財産調査」なのか、「特定の隠し財産の発見」なのか、目的が具体的に記されているかをチェックします。
調査費用に関しては、着手金や成功報酬、追加費用が発生する条件などが明確に示されているかを確認し、不明な点があれば必ず質問してください。
調査期間についても、開始日と終了予定日が記載されているかを確認しましょう。
調査によって得られた情報の取り扱い方法では、個人情報の保護や調査結果をどのように報告してもらえるか、秘密保持に関する条項が明記されているか、確認が必要です。
口頭での約束だけでなく、すべての条件が契約書に書面で残されているかどうかが、後々のトラブルを防ぐうえで重要となります。
調査実施から報告書提出までの期間
探偵に相続財産調査を依頼してから、実際に調査が実施され、報告書が提出されるまでの期間は、依頼内容や故人の状況によって大きく異なります。
一般的な調査であれば、数週間から1ヶ月程度で結果が出ることが多いですが、複雑なケースや広範囲にわたる調査が必要な場合は、数ヶ月かかることも珍しくありません。
調査期間中は、探偵事務所から定期的に進捗報告がもらえるのが一般的で、依頼者は調査がどのように進んでいるかを把握可能です。
調査が完了すると、探偵から詳細な調査報告書が提出されます。
報告書には、発見された財産や負債の具体的な情報、調査の過程で得られた証拠などがまとめられており、今後の遺産分割協議や法的手続きを進めるうえで重要な資料となります。
受け取ったらすぐに内容を確認し、不明な点がないか探偵に確認しましょう。
相続財産調査の実例とトラブル事例
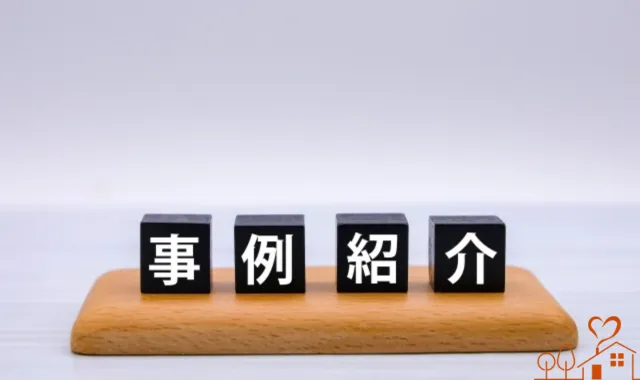
相続財産調査は、故人や遺族の事情によってさまざまな実例が存在します。
ここでは、相続財産調査での事例やトラブルに発展した事例を紹介します。
隠し口座が発見され遺産分割に影響した事例
Aさんのご家族は、父親が亡くなった後、遺産分割協議を進めていました。
父親の財産は、自宅と預金口座、そして若干の株式があることは把握できていましたが、母親が「他にも何か財産がある気がする」と不安を口にしたため、念のため探偵に調査を依頼することに。
探偵が調査を進めると、公的には知られていない、地方銀行の支店に開設された隠し口座が発見され、予想をはるかに超える数千万円の預金があり、父親が長年にわたってコツコツと貯めていたことが明らかになったのです。
隠し口座の存在が明らかになったことで、当初の遺産分割協議は白紙に戻り、改めて財産全体を再評価して協議をやり直すことになりました。
結果的に、相続人全員が納得できる公正な遺産分割が実現し、母親の不安も解消されました。
借金が判明し相続放棄を選択した事例
Bさんは、父親が亡くなり、遺産の相続手続きを進めていました。
父親の財産は、自宅と少額の預貯金のみだと思っていましたが、生前の父親はあまりお金の話をする人ではなく、借金がある可能性も否定できませんでした。
そこで、探偵に財産調査を依頼することに。
探偵が調査を進めると、友人や知人との個人的な借用書が複数発見されたほか、信用情報機関への情報開示も併せて行った結果、消費者金融からの多額の借入金があることが判明したのです。
プラスの財産をすべて合わせても、借金の総額には遠く及ばないことが分かり、Bさんは弁護士と相談し、相続放棄を選択しました。
不動産の存在が確認でき相続税申告が変わった事例
Cさんのご家族は、父親が亡くなり、相続税の申告を税理士に依頼しようとしていました。
父親の財産は、都内にある自宅と預貯金、そして少しの株式があることは分かっていましたが、税理士から「故人が地方に不動産を所有している可能性はないか」と問われ、心当たりがなかったため、探偵に調査を依頼することにしました。
探偵が父親の出身地や過去の住所履歴を丹念に調査したところ、数十年前から父親名義のままになっていた地方の土地と、そこに建つ古い家屋が発見されたのです。
これらの不動産は、家族の誰も存在を知らず、固定資産税の通知書も昔から届いていなかったため、全く把握できていませんでした。
これにより、相続財産の総額は当初の予想を大きく上回り、相続税の申告内容も修正が必要となりました。
探偵に依頼して相続の財産調査をスムーズに進めよう

相続における財産調査は、故人の思いを汲み取り、遺産を巡るトラブルを未然に防ぐための重要なステップです。
しかし、財産状況が複雑であったり、相続人同士で不信感があったりする場合、自分たちだけで調査を進めるのは困難といわざるを得ません。
そんな時こそ、プロの探偵に依頼することを検討してみてください。
探偵は、公的な調査では見つからない隠し財産や、隠れた借金を発見する能力に長けており、第三者の視点から客観的な情報を提供してくれます。
相続人同士の不信感を解消し、遺産分割協議をスムーズに進めることが可能になるでしょう。
また、探偵が作成する詳細な報告書は、法的手続きの際にも有効な証拠となります。
実際に相続財産調査を希望する場合は、名古屋東海ファミリー探偵事務所にご相談ください。
隠し財産の特定や相続人探し、遺言書の真偽判定など、相続に関するさまざまな調査に対応可能です。