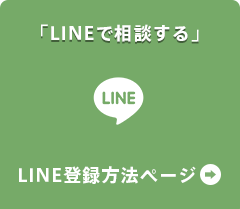お持ちのスマホやPCは知らず、知らずのうちに不正アクセス・ハッキングされている可能性があります。
ハッキング・不正アクセスが起こると、情報漏えいなど、企業や個人のブランドイメージを棄損するセキュリティ事故につながることもあります。
名古屋東海ファミリー探偵社では、デジタル端末の不正アクセス・ハッキングの調査を行っています。
この記事では、当事務所が実施する不正アクセス・ハッキングの調査について解説します。
ハッキング・不正アクセスでお悩みの方は、当事務所にご相談ください。
目次
不正アクセス・ハッキングの兆候

不正アクセス・ハッキングには兆候があります。
具体的には下記のような兆候があると、不正アクセス・ハッキングされている可能性が高いといえます。
- 端末の誤作動が増える
- 動作が異常に重くなる・遅くなる
- 覚えのないプログラムが自動起動する
- ファンが常時回転して、異音がする
- ハッキングされたと脅迫メッセージが表示される
- パスワードが勝手に変更されている
- 管理者権限が勝手に変更されている
- データ通信量が異常に増加している
- マイクが勝手に起動している
- Webカメラが勝手にオンになる
- 送信履歴に身に覚えのないメールがある
- 普段使わないアプリがバックグラウンドで動作している
- 身に覚えのないクレジットカードの利用
これらの変化は日常的な不具合と区別がつきにくいため、見過ごされがちですが、複数の症状が同時に現れた場合は警戒しましょう。
近年、個人や企業を問わず不正アクセス・ハッキング被害が急速に増加しています。
セキュリティ会社大手の株式会社サイバーセキュリティクラウドによると、世界中で1日に330万回のサイバー攻撃を検知し、決して他人事ではない状況です。
被害を最小限に抑えるためには、不正アクセスやハッキングの兆候を早期に発見する必要があります。
不正アクセス・ハッキングされてしまうとその問題が解消されることはありません。
不正アクセス・ハッキングの調査は、その問題を解消できるたった1つの方法です。
不正アクセス・ハッキングのリスク

不正アクセスやハッキング被害を受けた場合、単なるシステムの不具合や一時的な障害では済みません。
具体的には下記のようなリスクがあります。
- 個人情報漏えい
- 金融被害の拡大
- 企業機密情報の流出による競争力の低下
- 法的責任と社会的信用の失墜
- プライバシー侵害と精神的被害
- 業務停止と復旧コスト
パソコンやスマホには多くの個人情報や機密データが保存されているため、これらの情報が悪意のある第三者の手に渡ることで、大きな被害が発生する可能性があります。
自身で行える不正アクセス・ハッキングへの対策

不正アクセスやハッキングの被害を防ぐために、個人や企業が実施できる基本的な対策は数多く存在します。
これらの対策を適切に実施することで、サイバー攻撃によるリスクを大幅に減少させることができます。
定期的なソフトウェアのアップデートの徹底
オペレーティングシステムやソフトウェアの定期的なアップデートです。
セキュリティパッチが提供される度に速やかに適用することで、既知の脆弱性を悪用した攻撃を防ぐことができます。
また、信頼できるセキュリティソフトウェアの導入と定期的なウイルススキャンの実施も欠かせません。
強固なパスワードを設定し・定期的に変更する
パスワード管理についても、強固なパスワードの設定と定期的な変更が必要です。
単純な文字列や個人情報に基づいたパスワードは避け、大文字・小文字・数字・記号を組み合わせた複雑なものを使用しましょう。
可能であれば、二段階認証や多要素認証の設定により、セキュリティをさらに強化することをおすすめします。
基本的な行動指針を決める
技術的な対策と同様に重要なのが、日常的な行動における対応です。
- 不審なメールの添付ファイルやリンクをクリックしない
- 知らないUSBメモリやCD-ROMをパソコンに接続しない
- 公共のWi-Fiでは重要な情報をやり取りしない
基本的な指針を決めることで不正アクセス被害防止につながります。
名古屋東海ファミリー探偵社が実施する不正アクセス・ハッキングの調査

個人や企業での対策だけでは限界がある場合、専門的な調査会社のサービスを活用することで、より高度で効果的な対策を実施することができます。
調査会社では、最新の技術と豊富な経験に基づいた総合的なセキュリティサービスを提供しています。
デジタルフォレンジック調査による詳細分析
デジタルフォレンジック調査は、探偵事務所の最も重要な調査の1つです。
この調査は、コンピュータやネットワークシステムに残された微細な痕跡まで追跡可能で、不正アクセス・ハッキングの全容を明らかにできます。
マルウェアの感染経路の特定、不正アクセスの侵入手法の解明、情報漏洩の範囲確認など、困難な高度な調査が可能です。
また、攻撃者が隠蔽工作を行っていたり、ログを削除していたりする場合でも、専門的な技術により復元・解析を行うことができます。
これにより、被害の全容把握と適切な対策の立案が可能になります。
侵入テストとセキュリティ診断
当事務所では、実際のハッカーの手法を用いて企業のシステムに侵入を試みる「ペネトレーションテスト」を実施し、セキュリティの脆弱性を詳細に評価します。
このテストにより、従来の対策では発見できなかった潜在的なリスクを明らかにし、攻撃者による侵入を未然に防ぐための具体的な改善策を提案します。
ネットワーク構成の分析、アプリケーションの脆弱性検査、従業員のセキュリティ意識調査など、多角的な観点からセキュリティレベルを評価し、個々の企業に最適化された対策を立案します。
法的対応と報告書作成のサポート
不正アクセス・ハッキングによる被害を受けた場合、監督官庁への報告や顧客への通知、場合によっては法的措置の検討が必要になります。
調査会社では、これらの対応に必要な証拠収集と詳細な調査報告書の作成を行い、企業の法的責任を適切に果たすためのサポートを提供します。
特に個人情報保護法による報告義務や、業界固有の規制への対応について、専門的な知識に基づいた適切なアドバイスを受けることができます。
これにより、法的リスクを最小限に抑えながら、適切な対応を実施することが可能です。
当事務所が不正アクセス・ハッキングを解決した事例3選

実際の調査事例を通じて、調査会社がどのように不正アクセス・ハッキング問題を解決したか具体的に見てみましょう。
事例1:スマートフォン乗っ取りによる個人情報流出とストーカー被害
30代女性の会社員から「元交際相手によるストーカー被害を受けており、自分の行動が全て監視されているような状況が続いている」との相談が寄せられました。
相談者は、訪れた場所や会った人について、なぜか元交際相手が詳細に知っていることに不安を感じ、スマートフォンが何らかの方法で監視されている可能性を疑っていました。
当事務所の調査の結果、スマートフォンに監視アプリが密かにインストールされていることが判明しました。
このアプリは、GPS位置情報、通話履歴、メッセージ内容、写真、連絡先などの個人情報を外部サーバーに送信する機能を持っており、元交際相手が遠隔地からリアルタイムで監視できる状態になっていました。
また、SNSアカウントのパスワードも変更されており、投稿内容や友人との会話も監視されていた実態が明らかになりました。
調査会社では、監視アプリの完全削除とセキュリティホールの修正を実施しました。
また、すべてのアカウントパスワードの変更、二段階認証の設定、不要なアプリの削除などの包括的な対策を行いました。
調査報告書は警察への相談時の証拠として活用され、ストーカー規制法に基づく法的措置が取られました。
さらに、今後の再発防止のため、スマートフォンの適切な管理方法とセキュリティ対策についての指導も実施されました。
事例2:在宅勤務中のパソコン遠隔操作による機密情報窃取
40代男性の会社員から、「在宅勤務中に使用している個人パソコンが遠隔操作されているようで、会社の機密情報が漏れている可能性がある」との緊急相談がありました。
相談者は、パソコンの画面が勝手に動いたり、ファイルが移動されたりする現象を目撃し、同時に会社内で自分しか知らない情報が第三者に知られている事実を発見しました。
マルウェアの完全駆除とシステムの修復を実施し、盗まれたデータの範囲と内容を詳細に特定しました。
企業への報告により、該当する顧客への通知と謝罪、セキュリティ対策の強化が行われました。
また、在宅勤務環境のセキュリティ向上のため、業務用と私用の完全分離、VPN接続時の多要素認証導入、定期的なセキュリティ教育などの包括的な対策を実施しました。
事例3:オンラインゲームアカウント乗っ取りと仮想通貨詐欺被害
20代男性の大学生から「オンラインゲームのアカウントが乗っ取られ、ゲーム内の貴重なアイテムが盗まれた上、仮想通貨を要求する脅迫メールが届いている」との相談がありました。
相談者は長年プレイしていたオンラインゲームで、希少価値の高いアイテムやキャラクターを多数所有していましたが、ある日突然ログインできなくなりました。
その後、ゲーム内の全財産が他のプレイヤーに譲渡されており、さらにゲームアカウントに登録していたメールアドレスに「アカウントを返してほしければ仮想通貨を送金しろ」という脅迫メッセージが送られてきました。
また、同じメールアドレスで登録していた他のサービスにも不正アクセスが発生していることが判明しました。
調査の結果、フィッシング詐欺サイトでゲームアカウントの認証情報が盗まれていたことが分かりました。
攻撃者は巧妙に作られた偽のゲーム公式サイトを作成し、「期間限定イベント参加のためのログインが必要」という内容のメールでユーザーを誘導していました。
まず、すべての関連アカウントのパスワードを一斉変更し、二段階認証を設定しました。
また、フィッシング詐欺の手口と対策について詳細な説明を行い、今後同様の被害を防ぐための知識を提供しました。
早期発見と専門的な調査により、被害の拡大を防ぎ、適切な対策を講じることができます。
一人で悩まず、専門家に相談することで、解決策を見つけることができます。
不正アクセス・ハッキングに関するよくある質問3選
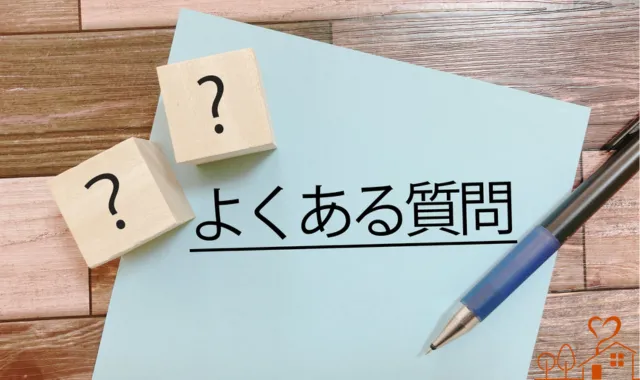
質問1:不正アクセス・ハッキングの調査費用はどのくらいかかりますか?
不正アクセス・ハッキング調査の費用は、調査の規模や内容によって大きく異なります。
個人のパソコンやスマートフォン1台の簡易調査と企業の大規模なネットワーク全体を対象とした詳細調査では、まったく調査費用が異なります。
質問2:不正アクセス・ハッキング調査期間はどのくらいかかりますか?
調査期間は、被害の規模や調査の複雑さによって大きく左右されます。
簡易的な調査であれば数日から1週間程度で完了しますが、大規模な企業ネットワークの詳細調査では数週間から数ヶ月を要する場合もあります。
質問3:本当に不正アクセス・ハッキングされているかわからないのですが、相談できますか?
疑いの段階でも相談可能です。
当事務所では初回相談を無料で実施しており、症状をお聞きした上で、ハッキングの可能性を判断し、必要に応じて詳細調査を提案します。
「なんとなくおかしい」と感じる場合でも、遠慮なくご相談ください。
不正アクセス・ハッキングの調査は名古屋東海ファミリー探偵社にご依頼を!

不正アクセス・ハッキングは現代社会において避けることのできない深刻な問題です。
日本国内だけでも多くの不正アクセス・ハッキングが検知されており、個人から大企業まで、誰もが被害者になる可能性があります。
しかし、適切な知識と対策により、被害を未然に防いだり、最小限に抑えたりすることは可能です。
しかし、巧妙化する不正アクセス・ハッキングに対しては、個人や企業の努力だけでは限界があるのも事実です。
当事務所では、デジタルフォレンジック技術による詳細な分析、24時間365日の監視体制、法的対応のサポートなど、個人では実現困難な高度なサービスを提供しています。
不正アクセス・ハッキング被害に兆候を感じたら、当事務所の調査をご活用ください。